此度のパンデミックにより、以前には想像もしなかった状況が、今、日常となっています。
歴史を眺めると、今の我々と同じような激変を、幾度となく経験してきたことに気付かされます。
疫病が社会変革をもたらすことを、古代ギリシャ、古代ローマ、後漢末の中国を実例にご解説頂きました。
有り難うございます。
パンデミックは農耕から
狩猟採集 → 群れ
牧畜 → 家畜と人の継続的な濃厚接触 → 変異 → 家畜から人への感染
農耕 → 定住 → 村 → 町 → 都市 → 密集生活 → 爆発的感染
アテネの疫病
ペロポネソス戦争(B.C.431ー404)
スパルタ VS アテネ
ペリクレスの提案により、全アテネ市民は城壁内に退避、籠城。
アテネ領土は千葉県と同等。極度の密集状態となる。
当時エジプト、リビア、ペルシャ、エーゲ海東部で流行していた疫病が発生。
『突然、頭部が強熱におそわれ、眼が充血し炎症を起こした。口腔内では舌と咽頭がたちまち出血症状を呈し、異様な臭気を帯びた息を吐くようになった。これに続いてくさみを催し、咽頭が痛み声がしわがれた。まもなく苦痛は胸部に広がり、激しい咳をともなった。症状がさらに下って胃にとどまると吐気を催し、医師がその名を知る限りの、ありとあらゆる胆汁嘔吐がつづき、激しい苦悶をともなった。ついに患者の多くは、激しい痙攣とともに、空の吐気に苦しめられたが、これらの症状は人によって胆汁嘔吐のあとで退いていく場合と、さらに後まで長びく場合と、二通りが見られた。皮膚の表面に触れると、さほど熱はないが、蒼白味が失せ、赤みを帯びた鉛に、ごく薄手の外衣や麻布ですら身につけると我慢ができず、裸体になるほかは堪えようがなく、できることなら冷水に身を投げいれれば、どれほど心地よかろうかと思うほどであった。じじつ、看とる人もいない多勢の疫病患者は、間断ない渇きに苦しめられ、貯水池に跳込んで熱と渇きを癒やそうとした。しかし幾ら水を飲めども渇きはいっこうに癒やされなかった。その間一時も体を安静にしておくことも眠りにつくこともできず、苦痛にたいしても予想に反する抵抗力を示しつづけ、大多数の者は幾分かの体力をまだ残しながら、高熱のために七~九日目に死んでいった。さもなくば、この症状を脱出しても、病勢はさらに腸部に下り、ここに激甚な潰瘍を生じると同時に、水のような下痢に襲われ、このために体力を消耗して、やがては衰弱死をとげることとなった。というのはそれまでに、最初に頭部に症状を発した疫病は、上からはじまって体のすみずみまで侵していたからである。たとえその最悪の症状から辛うじて生きのびた人間も、体の末端部分に後遺症をとどめることとなった。病は恥部や手足の末端部までもおそったために、病が治っても多くのものは、これらの部分の機能をうばわれた。また盲になったものも幾人かいる。またあるものは、恢復の兆しがみえるとたちまち、いっさいの事物に関する記憶を完全に失い、自分自身も親類友人の別も判らなくなってしまった。』
『患者たちは、あらゆる神殿に助けを求めて嘆願につめよせ、予言の社やその他これに類する神力にすがったが、何の利益も得られず、やがてはみな病苦に打負かされて、もはやこのような場所に寄りつかなくなってしまった。』(トゥーキュディデース 「戦史」上 久保正彰訳 岩波文庫)
B.C.429 ペリクレス死去
その結果、倫理観は崩壊し、衆愚政治が横行し、アテネは敗北を喫する。
新しき世界
デモクリトス(B.C.460頃-370頃)
原子論。
古代ギリシアに於ける唯物論の完成。
ソクラテス(B.C.469頃-399)プラトン(B.C.427-347)
イデア論。
新たな倫理観の探求。
アントニヌスの疫病
第六次パルティア戦争(AD.161-166)
マルクス・アウレリウス・アントニヌス(AD.121-180)
ローマ帝国 五賢帝時代最後の皇帝
対パルティア戦役の帰還兵により、ローマに天然痘と思われる疫病がもたらされた。
この疫病はパンデミックとなり、アントニヌスの疫病と呼ばれる。
新しき世界
ミトラ教
インド、イランに共通するミスラ神に対する信仰が、ヘレニズム時代の文化交流により地中海世界に伝わり、成立した宗教。
キリスト教
死後の世界を信じ、死を恐れず、献身的に介護する姿が、パンデミックを追風として信仰者を増やしていく。
後漢末の疫病
マルクス・アウレリウス・アントニヌスの使節
AD.166 大秦国王安敦の使節 後漢 日南郡(ヴェトナム)に訪れる
ヴェトナム南部のオケオ遺跡からは、アントニウス・ピウスやマルクス・アウレリウス・アントニヌスの時代の金貨が発見されており、交易ルートが確立されていた事が伺える。
黄巾の乱
AD.183 疫病の流行
AD.184 黄巾の乱
張角が創始した太平道と呼ばれる教団が起こした反乱。
太平道は、疫病の治療を行い勢力を伸ばしていた。
新しき世界
中華世界の崩壊
三国鼎立時代を経て、晋による統一を以て、戦乱の世は平定されたかに見えた。
しかし、後継者争いに異民族を巻き込んだ事から、黄河流域が異民族に支配される時代へと突入していくこととなる。
私見
ギリシャ・ローマ世界が、多神教から一神教へと向けて静かに変容していくのに対し、中華世界は、一気に崩壊するかに見えて、実は何も変わっていない。
ギリシャ・ローマ世界
デモクリトス(B.C.460頃ー360頃)
デモクリトスは、エーゲ海北岸のイオニア人の植民都市アブデラ出身。アテネを訪れた事があるようだが、誰も彼をそれと気付かなかった。
『というのも、私はアテナイへやって来たが、誰も私をそれと知る者はなかった。』(デモクリトスの断片 fr.116)
彼は、感覚の世界を否定し、無機質な原子と虚ろな空虚による世界観を提示した。
『色は慣習の上であるにすぎず、苦さも慣習の上であるにすぎない。真実には不可分者(アトモン)と空虚(ケノン)あるのみ。』(fr.125)
白紙上(空虚)に、単音以外の意味のない表音文字(不可分者)が配列され、イメージの世界が表れる事と近似している。
人はこの配列を、絶えず生み出し続ける。
『人間、日毎に新しきを思惟する者たち。』(fr.158)
白紙(空虚)は、幾らでもある。
『あらぬもの(非存在)は、あるもの(存在)にすこしも劣らずある。』(fr.156)
このようにして、実在とイメージの世界を混同していくことになる。
『宇宙万有について、私はつぎの点を主張する。――人間は、私たち全ての者が知っているところのもの・・・・・・。』(fr.165)
但し、必然の生み出す実在と、偶然の生み出すイメージの世界の違いを認識し、実在を僅差に於いて優位に見ていた様である。
『偶然(テュケー・人の生み出す偶然)は(時に)莫大な贈物をくれるが、当てにならない。だが自然は自ら足りている。それゆえ、自然(ピュシス)は、より僅かだが確実(な力)によって、希望(空頼み)の与えるより大きな贈物に勝るのだ。』(fr.176)
このような世界観に於いて、偶然の支配するイメージの世界に身を委ねていては、全てがカオスに陥ってしまう。故に、正しく秩序ある文章が成立する様に、正しさを与える何かに対する探究が求められる。
『愚人は偶然(テュケー)の贈物によって形づくられるが、この種のことがらをよく理解している者は、知恵(ソピエ)の贈物によって形づくられる。』(fr.197)
この知恵を神々に求めるのだが・・・。
『神々は人間どもに、昔も今も、あらゆる善きものを授け給う。だが、悪しきもの、害あるもの、無益なものはいっさい、これを、神々は人間どもに、昔も今も、与えたもうたことはないのだ。むしろ人間どもの方が、知性(ヌウス)の盲目と無思慮から、その種のものに自ら近づくのである。』(fr.175)
本来ギリシャ神話の神々は、人為の及ばぬ自然現象がもたらす災いと恩恵に対して、それを理解し、より多くの恩恵を得るために、人々の行為を規制するイメージであった。災いと恩恵の両義性を持つからこそ個性的であり、善悪入り乱れた世界観がそこにはあった。
然るにこの断片(fr.175)は、神々は恩恵しかもたらさないと主張する。この主張は、世界観の断絶と見てよいだろう。
神々は個性を失った。全員善良になってしまった。
更に、全てが「人間ども」の責任であったとするならば、それは人間の無力さに対する悲嘆の現れとして認識されよう。しかし、実際問題その逆である。全てが人間の責任であると宣言したのは、人間に正しい判断を下す能力があると確信したからである。つまりは、神々に対する、理性の勝利宣言である。
神々に縋ったところで無駄であるとの認識が、確実にそこにはあった。
デモクリトスは、その明るさから、「笑う人」と呼ばれる。
ソクラテス(B.C.496頃ー399)
デモクリトスは、ソクラテス以前の哲学者に分類されるが、ソクラテスよりも若い。
ソクラテスは、アテネに生まれ、その生涯のほぼ全てをアテネで過ごした。
その後半生はペロポネソス戦争と重なり、終戦後、弟子に与えた影響を敗戦の責任として問われ、死刑を宣告された。
事の発端は、デルフォイの神託から始まる。
ソクラテスの友人であるカイレフォンが、デルフォイに赴き、ソクラテス以上の賢者がいるかと問うた。それに対し、巫女は一人もいないと答えた。
訝しく思ったソクラテスは、己より賢いと思われる者たちを訪ね歩き、神託の否定を試みる。
しかし彼は、己が無知である事を知っているという点に於いて、神託の正しさを確信する様になる。
この様にして、彼は次の如き観念に捕らわれる。
『アテナイ人諸君、私は誓っていうが――なぜなら諸君には真実を語らなければならないから――、私は実際ほぼ次の如きことを経験したのである。即ち神意に従って探究した結果、私は、最も令名ある人々はほとんどすべて最も智見を欠き、これに反して尊敬せらるること少なき人々がむしろ智見において優れていることを認めた。』(「ソクラテスの弁明」第七章より)
平時ならばともかく、戦時に於いてこのような考え方が浸透していては、まとまるものも纏まらなくなってしまうであろう。「最も令名ある人々」を否定する行為は、既存の価値体系に留まらず社会体制の崩壊をももたらす。事実、弟子のアルキビアデスはスパルタに亡命し、機密情報を漏洩し、スパルタの戦略に積極的に寄与した。愛国心が欠落している。弟子のクリティアスは、スパルタ傀儡政権の三十人僭主政に於いて、粛正を行った。伝統を重んじていれば、言わずとも皆了解するものである。しかし、理性だけでどうにかしようとすると、為すべきことが個人の頭の中で構築されるだけで、全く普及していない。故に、意見の異なる者を粛正する、恐怖による支配以外の選択肢がなくなってしまう。普及に時間をかけている余裕は無い。普及したところで、検証もされていない。理性を絶対視したフランス革命にも、同じ結果をもたらした。共産主義革命も又同様である。激昂の矛先が向けられたとしても、何の不思議もなかろう。「弁明」に登場する「ソクラテス」は、自らの確信が何をもたらしたかを、全く理解していない。
ソクラテスは、概念を絶えず抽象化する方法論を生み出したが、弟子のプラトンに於いて、その到達点としてのイデア界が想定される。
プラトン(B.C.427ー347)
中華世界
中華世界の再興は、AD.979の宋による統一まで待つことになる。その間800年。

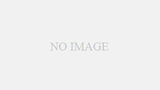
コメント