『中国=文化と思想』 林語堂(著) 鋤柄治郎(訳) 講談社学術文庫 1999
原書”My Country and My People” 1935年ニューヨークにて出版
パール・バックの序文
「喜ばしいことには、中国には混迷の時代にあても自分を失うことのない偉大な魂を持つ、少数の例外者がいたのです。彼らはあるがままにこの人生を観照することのできるユーモア(何代にもわたり機知と学問を傾けて育てた素晴らしいユーモアである)を持ち、他の文明を理解するのと同じように自国の文明を理解しうる聡明さを備え、彼らに固有なもの、すなわち純粋に彼ら自身のものを選択する賢明さを持っているのです。長い間私はこうした少数の作家の中から誰かが私たち西洋人のために彼ら自身の中国を語ってくれることを、中国の基本的精神を余すことなく反映した真実の書を書いてくれることを待ち望んでいたのです。私は何度熱い期待と希望を抱いてこうした書物を繙いたことでしょう。しかしその都度に私は失望と落胆のうちに本を閉じねばなりませんでした。そこには真実が書かれていなかったからです。また誇張に過ぎていたからです。ある本は国家の偉大さを喧伝しようとする余り、不必要な弁護までしていたからです。こうした著作は外国人の受けを狙って書かれたもので、中国人には何ら益するところのない価値のないものでした。」
「中国に関する著作で本当に価値を持つ著作とは、前述のような書物ではないのです。それは率直で忌憚のない考えを述べたものでなくてはなりません。なぜなら真の中国人は誇り高い民族であり、自身と自身の方法に対してもまた十分に率直であり忌憚ないと誇り得るからです。また理解において知恵と洞察力を備えていなければなりません。なぜなら中国人は人類の心の理解において豊かな知恵と洞察力を持っているからです。書物はユーモアを湛えていなければなりません。なぜならユーモアは中国人の本質を構成する一部であるからです。こうした穏やかで、円熟した、深いユーモアは人生に対する悲劇的な認識と容認に基づくものなのです。また書物は流麗にして正確、かつ優美な文章で綴られていなければなりません。なぜなら中国人は常に正確さと優美さを重視してきたからです。こうした書物を書くことができるのは他でもない中国人自身なのです。しかし果たして中国にこのような人物がいるのかどうか私は少し疑問を感じ始めていたところです。」
「しかし突如として、過去の偉大な著作の出現がそうであったように、本書もまた突如として我々の前に出現したのです。本書は前述のあらゆる要素を満たしているのみならず、そこには真実を覆い隠そうとする意図は微塵もなく、真実に溢れたものでした。その筆致は誇り高く、ユーモラスで流麗、厳粛でありながら面白く、また古今の中国に対して鋭く正確な理解を示しています。本書はこれまでに出版された中国を論じた著作の中で、最も真実みに溢れ、最も造詣が深く、最も完全で、最も重要な著作であると私は考えます。そして特筆すべきは、本書が一人の中国人、しかも歴史の中にしっかりと根を生やし、現在見事に見事に花咲かせている現代の中国人によって書かれたことでしょう。」
自序
第一部 背景
巻頭言
第一章 中国人
北方と南方
退化
新しい血の注入
文化の安定性
民族の幼年期
第二章 中国人の性格
円熟
忍耐
無関心
老獪
平和主義
足るを知る精神
ユーモア
保守主義
第三章 中国人の精神
知恵
女性的性格
科学精神の欠如
論理
直感
想像力
第四章 人生の理想
人文主義
宗教
中庸の道
道教
仏教
第二部 生活
序言
第五章 女性の生活
女性の従属的地位
家庭と結婚
理想の女性
女子教育
恋愛と求婚
娼婦と妾
纏足
女性の解放
第六章 社会生活と政治生活
社会性の欠如
家族制度
「閨閥主義」「不正」「礼俗」
特権と平等
社会階級
陽の三要素「官僚」「郷紳」「土豪」
陰の三要素「面子」「運命」「恩恵」
村落制度
仁政
第七章 文学生活
特徴
言語と思想
学問
学府
散文
文学と政治
文学革命
詩歌
戯曲
小説
西洋文学の影響
第八章 芸術生活
芸術家
書道
絵画
建築
第九章 生活の芸術
人生の楽しみ
住宅と庭園
飲食
結語――人生の終焉
訳者あとがき
私見
後日更新

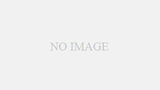
コメント