新時代に於ける対立構造は、恐らくここに帰結するのではないでしょうか。
貴重な示唆を頂きました。
有り難うございます。
江戸時代のユーラシア大陸
中東 オスマントルコ帝国
北 ロシア帝国
南 ムガール帝国
東 清
全て官僚制独裁国家
20世紀のユーラシア大陸
中東 混乱
北 ソビエト連邦 官僚制独裁国家
南 インド共和国 民主主義国家
東 中華人民共和国 官僚制独裁国家
中東
トルコを例外として民主化を経ずに独裁化。
トルコ
ケマル・パシャの指導の下、民主化。
しかし、エルドゥアン現政権により独裁化が進められている。
ソビエト連邦
民主化を経ずに共産化。
冷戦後崩壊するが、プーチンによる独裁が続く。
中華人民共和国
民主化を経ずに共産化。
鄧小平の下、経済は自由化するが、未だ民主的選挙は実現していない。
問い
なぜ独裁に引寄せられるのか?
ウィットフォーゲル
Karl August Wittfogel 1896-1988
第一次大戦後スパルタクス団に入党し、社会主義の理想を信じ、運動を行う。
専門は中国史。
ナチ政権下にて逮捕されるが、後にアメリカへ亡命。
第二次大戦後、ソ連によるドイツ解放を喜ぶが、東ドイツに於ける独裁に失望。
なぜ社会主義の理想が歪められたのか研究を始める。
そして、マルクスによるアジアの専制国家についての記述に注目する。
アジア的生産様式
マルクスの言葉。
一人の君主がいて、多くの官僚により人民を一方的に支配する様式。
ボトムアップは無い。
東洋的専制理論
ウィットフォーゲルの結論。
アジア的な生産様式が、ソ連と中共に受け継がれたと主張。
1. 大河の水をコントロールし灌漑農業を行う「水力国家」では、専制と官僚システムが最も効率的。
2. こうして生まれた帝国は、周辺の諸民族を従属させ、この体制を受容させる。
3. このシステムは遊牧民のモンゴル帝国に採用され、モンゴルの支配を受けたロシアにも移植された。
4. 帝国の支配を免れた西欧と日本には、専制国家体制が根付かなかった。
参考「東洋的専制」
Topic ペルシャ戦争 スパルタ代表使節、ペルシャ高官に語る
「スサへの道で、スパルタの使節はペルシャ高官に迎えられた。彼は使節に、彼らが大王に従えさえすれば、故国に於ける有力な地位を与えようと申し出た。ところがあらゆる自由人にとって幸いな事に、ヘロドトスは彼らの返答を残しておいてくれた。」
「ヒュダルネスよ、貴方は一面的な助言者である。貴方は事柄の反面だけの経験しか無く、他の部分は貴方の知識の外にある。奴隷の一生を貴方は理解するが、しかし決して自由を味わった事の無い貴方は、それが素晴らしいものであるかどうかを教える事は出来ない。ああ、貴方が自由が何であるかを知ったら、貴方は槍だけではなく斧を持ち出して戦うよう、我々に命令するに違いない。」
「文明の生態史観」 梅棹忠夫
ユーラシア内陸部 → 独裁化
ユーラシア外縁部 → 公共の精神に基づく統治 主に日欧
結論
遊牧民に蹂躙された地域は、独裁化する。
私見
より単純に理解可能であろうと思われる。
狩猟採集民族及び農耕民族
環境を知悉することにより、環境を有機的に捉え、自らを含め一つのゲシュタルトとして認識している。
それ以外の外界は異質な世界であり、脅威として認識される。
隣人はゲシュタルトに含められ、自己と同一視される。
抽象的に纏めると、
狩猟採集民族及び農耕民族は、隣人を含め、環境を自己同一視する。
ここに公共の理念が生じる。
遊牧民族
環境に対し、ゲシュタルトと呼べる程の一体感は無い。
ゲシュタルトの境界は、家畜を含めた共同体までとなる。
移動を繰り返すので、外界との交流は頻繁に生じる。
交易は生産者の側から見て、余剰生産の譲渡と呼べる。
本来、余剰品を安定的に生産することを目的に生産活動を行っているわけではない。
これに対し、遊牧民が譲渡に不足を認識した時、奪おうと思うならば、そこにはある。
故に収奪が発生する。
遊牧民が交易品の安定的生産を目的として支配を行った場合、被支配者である奴隷は、家畜の延長線上に位置付けられる。
家畜が肉を提供するように、労働が要求される。
家畜が司牧されるように、奴隷は管理される。
管理する為に、官僚制が発生する。
奴隷化する以前のゲシュタルトは、当然のごとく崩壊する。
奴隷は、求められる役割を自己同一視することが、強要される。
抽象的に纏めると、
遊牧民族は、家畜を含め、共同体を自己同一視する。
遊牧民族は、支配する他者を家畜の延長線上に捉える。
遊牧民族は奴隷に対し、求められる役割との自己同一化を当為と見做す。
感覚的に纏めると、
「俺たちが生きていくには、家畜に餌をやらなきゃならねえ。満足してもらうには、それだけじゃ足りねえ。色々持ってる奴らがいるから、そいつらと交換しよう。おい、前は譲ってくれたじゃねえか、何でだよ。持ってんじゃねえか、許せねえ、寄こせ。ふざけた奴らだ、家畜の方がまだましじゃねえか。俺が教えてやるよ。なんだよ、小難しいこと言ってんじゃねえ。黙って俺が言う通りにやれば良いんだよ。家畜の方がまだましだな。なんだって?家畜の分際で余計なことを考えんじゃねえ。」
これに対する感情が如何なるものであるかは、スパルタ人の拒絶が多くを語っている。
次の時代の世界の構造は、この感情を発するか否かによって線引きされる。
日本は今、発していない。
奴隷的生態の洗練
自己同一視する対象が、求められる役割に限定されることに対し、その軛からの解放は、自由と認識されよう。
しかし実質的には、自己同一視する対象の解放、別言すれば、知っている物事や人々を大切に思う感情が認められる事を意味する。
自由という言葉を使う時、何から解放され、何が認められるかを問題にしなければならない。それにより、自由の意味するものが全く異なってくるからである。
ともかく、奴隷からの解放は、人生の全てを賭けるに値するものではあるのだが、これとはまた別の選択肢もまた存在した。
それは、求められる役割のみに一生を捧げる生き方を、一層むしろ全面的に肯定してしまう事である。
その延長線上に、天職観念が存在する。
これは、自分から大切に思うという感覚では無く、祝福を受けるという受動的感覚である、という違いはあるのだが。
この件に関し多くを語ることは別の機会に譲るが、天職観念に至る経緯の一つとして、「バガヴァッド・ギーター」の一節を挙げておこう。
「海に水が流れ込む時、海は満たされつつも不動の状態を保つ。同様に、あらゆる欲望が彼の中に入るが、彼は静寂に達する。
アルジュナよ、これがブラフマンの境地である。
臨終の時に於いても、この境地にあれば、ブラフマンに於ける涅槃に達する。
彼にとって、この世に於ける成功と不成功は何の関係もない。また万物に対し、彼が何らかの期待を抱くこともない。
それ故、執着することなく、常に為すべき行動を遂行せよ。実に執着なしに行為すれば、人は最高の存在に達する。
心が平等の境地に止まった人々は、まさにこの世で生存(輪廻)を征服している。知性が確立し、迷妄無くブラフマンを知り、ブラフマンに止まる人は、好ましいものを得ても喜ばず、好ましくないものを得ても嫌悪しない。」
アルジュナは尋ねた。
「それでは、クリシュナ。人間は何に命じられて悪を行うのか。望みもしないのに。」
聖バガヴァッドは告げた。
「それは欲望である。それは怒りである。
この世で、それが敵であると知れ。
意(こころ)が平等の境地に止まった人は、まさにこの世で生存(輪廻)を征服している。
まさにこの世で、身体から解放される前に、欲望と怒りから生ずる激情に耐えうる者は、専心した幸福な人である。
私は全世界の本源であり、終末である。私よりも高いものは他にない。アルジュナよ、この全世界は私につながれている。
私は過去、現在、未来の万物を知っている。アルジュナよ、しかし何者も私を知らない。
この全世界は、非顕現な形の私によってあまねく満たされている。万物は私のうちにあるが、私はそれらの内には存在しない。
私はこの世界の父であり、母である。
主である。目撃者である。住処である。寄る辺である。友人である。本源であり、終末であり、維持である。」
「識扁」に随って、理に応じ要約すると、
「偉大な俺様に従っておけ。
それがお前にとっての幸福だ。
余計なことを考えるな。
それがお前を苦しめるのだ。」
となる。
これは、「ヨブ記」と類似している。

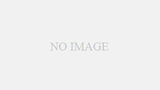
コメント