『イスラーム思想史』 井筒俊彦(著) 中公文庫 1991
第一部 イスラーム神学――Kalam
アラビア砂漠の精神とコーラン
「普通アラビア語でKalamと称され、イスラーム神学、思弁神学の名の下に知られているものは、思弁的論理的な方法によってイスラームの信仰上の難問を解決しようとする一種の知的運動である。」
「さてこの思弁神学発生の直接の源泉は何処にあったかというと、それが哲学的思惟とか神学的思弁や論証に全く無縁のコーランそのものであったのである。故にもし思弁神学の起りを理解しよびうとするならば、まず第一に、コーランの本質は何であるか、またどのような精神がこの比類ない経典を生み出したのであるかを識らなければならない。」
アラビア民族
「彼らの生活していたところは灼熱の太陽に焼ける荒漠たる砂漠であった。果ない砂漠を、僅かの草と水を求めて漂白して行く彼ら遊牧の民にとっては、遙か遠方にしたたる水滴の音を聞きつけ、或はまた、漠々たる砂原が天に接する地平の彼方に、かすかにうごめく動物の姿や、無上の憩いを与えてくれる木立を発見し、または地平線に巻起る砂塵を見て直ちに敵軍の陣形や数を知ることは、容易ならぬ生活上の重大事であった。」
「その昔、アテナイのギリシャ人は「美しくて善い」(kalos kagathos)ことをもって理想的な人物としたが、砂漠に移り歩くベドウィン達は「眼光射る如く、常に耳そばだて」ている男を理想とした。だから詩にもある通り、
その眼光刺す如く、顔色輝き、
性高潔に力強く、その耳はスィアマ(架空の、聴覚が極めて優れた動物)よりも敏し。
と称されることは、彼らの無上の名誉とする所であった。」
「かくてアラビアの文化は、その純アラビア性においては著しく視覚的・聴覚的な文化である。」
「アラビア人は、「物を視る」事にかけては、実に比類ない民族である。彼らは自分の身の廻りの、どんな微細なものでも見のがしはしない。どのように小さなものでも、彼らの驚くべき眼光に照し出されると、我々には思いもかけぬ姿を取って彼らの前に自己を示すのであった。そうして、こういう一々のものに彼らは特色のある名を付けた。彼らが視た全てのものが、一々別の名を受けた。例えばサンスクリットに典型的な形で見られるような、共通の要素を基とし、それに多の要素を色々に組合わせて新しい語を造る、いわゆる合成語は、個物を絶対的に尊ぶアラビア人の精神――そしてより一般的にはセム人の世界受容の根本的態度――に全く反するものであった。彼らの眼の及ぶ限り、あらゆるものは独立した名称を与えられたのである。」
「そしてこういう風に眺められた一々の物は、彼らの著しい感じ易い心に深い感動を与えた。この深い感動は直ちに美しいリズムをもったもった抒情詩となって表現された。」
「無道時代(イスラーム化される以前の古い、古い、純アラビア的時代)のアラビア人が創り出した文化的産物の中で、最も独特な、独特な、そして世界に誇り得る唯一のものは抒情詩であるとはよく人のいうところである。」
「彼らは個々の物を詳しく直感的に捉え、それから激しい感動を受けることにかけては天才的であったけれども、この感動と、その表現とは飽くまで印象的断片的であった。個々の感動を更に整理して、これに論理的構成を与えることは彼らのよくせぬ所であった。彼らの心裡には生々しい幾多の印象が雲集し、先を争って表現されようとしてはいたが、そこに論理的秩序は無かった。」
「ムハンマドは感覚的で非論理的なアラビア人の典型的な偉人であり、そのもたらしたコーランは、こういう視覚的・聴覚的な天才、非論理的な天才の生み出した驚異すべき産物である。」
「かくて、コーランは論理的に見れば矛盾に満ちている。」
「コーランはどんな経典にもまして、著しく視覚的であり、聴覚的な経典である。」
「古い砂漠のアラビア人は明らかにexistentia的であって、essentia的ではない。言い換えれば、彼らの世界観はSosein的ではなくてDasei的である。彼らが観るものは常にこの時、この場所という時空に制限された個々の物である。個別を超えた一般者には彼らは全然用がない。」
「物をいわゆる「永遠の相の下に」(sub specie aeternitatis)視るなどということは彼らの思いもかけない所であった。」
「新宗教の情熱に燃えるアラビアの回教徒達は預言者の死後たちまちのうちにメソポタミアを、シリアを、ペルシャを、トルコを席巻し、エジプトを取り、北アフリカ諸国を征服し、インドにまでその勢力を伸ばした。これらの様々な古代文化圏においてアラビア砂漠の現実主義、個物主義は全く異質的な精神に衝突し、それらとの対決を迫られた。」
「純アラビア砂漠的精神は後退し、そこにできた空間にビザンチン的キリスト教の神学が、古代ギリシャ的哲学精神が、ゾロアスタア教的二元論が、シリアの透徹した理性が、ヘレニズム的グノーシスと神秘主義が、目もあやに錯綜しつつ新しい思想を織り出して行く。しかも一方、砂漠精神を代表するコーランは一字一句が聖なる神の言葉として厳然としてそれらの思想潮流の前に立ちはだかる。そこに「異端」が生じ、「正統派」が成立する。それらの本質的に異なる諸思想傾向の衝突と融合と、次々に試みられる新しい総合の過程がイスラーム思想の歴史を構成する。」
イスラーム法学諸派の形成とその基本概念
思弁神学の発生
ムアタズィラ派出現まで
ムアタズィラ派の合理主義
アシュアリーの出現とその思想史的意義
イマーム・ル・ハラマインの思弁神学体系
ガザーリーにおける理性と信仰
第二部 イスラーム神秘主義(スーフィズム)――Tasawwuf
スーフィズムの起源
初期の修道者たち
修業道の理論的反省
神秘主義的思想形成の黄金時代
初期スーフィズム思想の黄金時代
第三部 スコラ哲学(Falsafah)――東方イスラーム哲学の発展
ギリシャ哲学の移植
最初の哲学者キンディー
「第二の師」ファーラービー
純正同胞会(Ikhwan as-Safa)
イブン・スィーナー(Avicenna)の哲学
ガザーリーの哲学批判
第四部 スコラ哲学(Falsafah)――西方イスラーム哲学の発展
「孤独の哲人」イブン・バーッジァ(Avempace)
イブン・トファイル(Abubacer)の哲学小説
イブン・ルシド(Averroes)の思想
イブン・アラビーの神秘哲学――西方から東方へ
後記
私見
後日更新

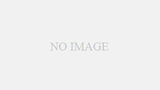
コメント