既得権益にしがみつく人々は、危機が訪れた時、一体何をしてくれるのでしょうか。
答えは簡単です。
既得権益にしがみついてくれます。
既得権益にしがみつくことしか知らないから、既得権益にしがみつくのです。
彼等は、優しく嗜めるように、膨大な知識を振りかざし、こう諭してくれるでしょう。
「君、必要なんだよ。もっと勉強したまえ。」
それに対し、こう答えてあげましょう。
「随分と小さく精密な箱庭ですね。」
彼等は、こう答えるでしょう。
「貴様、侮辱するのか!」
それに対し、こう答えてあげましょう。
「事実を言っているまででです。周りを見るべき時に、おもちゃに夢中になっている人にしか見えないんですよ。だってそうでしょ、今正に、そのおもちゃが壊されようとしている時に、貴方、それに気付いてないんですから。」
西ローマ帝国の滅亡前夜と、現在の日本が重なって見えました。
忠言として受け止めます。
有り難うございます。
AD.212 アントニヌス勅令
カラカラ帝(マルクス・アウレリウス・セウェルス・アントニヌス)により、全属州民にローマ市民権が与えられた。
元来ローマ市民権は、国防に参加する者に与えられた。
故に、国防とローマ市民としての自覚は、一体であった。
領土の拡大と共に分業化が進み、国防と直接関わらぬ市民が誕生したが、市民権の新規獲得には、国防への参加が必要とされた。しかし、カラカラ帝により市民権が無条件で開放されると、国防を自らの問題として意識する諸条件が失われていった。
市民である事は当り前の事となり、「国防によるローマ市民としての自覚」は、「既得権益の防衛による身近な所属集団への帰属意識」へと変わっていった。
AD.293 テトラルキア
ディオクレティアヌス帝により、ローマ帝国は四分割された。
ローマでは、共和制時代、毎年選ばれる2名の執政官により統治されていた。
執政官は政務と軍事を兼ねていた。一人が指揮官として前線に赴く時は、一人が政務を担当し、二人共に前線に赴く時は、後事を託される役職は決められていた。無能な者が選ばれたとしても、毎年選挙が行われる為、選び直せば良かった。
初期帝政時代、皇帝は次期皇帝に相応しい人物を養子とし、帝位を継承させた。これは、単純に嫡子不在によるものであるが、それが功を奏し、「無能」な皇帝が即位することは避けられた。しかし、マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝の嫡子であるコンモドゥス帝以降、皇帝暗殺による政権交代が頻発する。カラカラ帝以降は特に酷く、軍人出身の皇帝が乱立する「軍人皇帝時代」と呼ばれた。それに終止符を打ったのがディオクレティアヌス帝である。
ディオクレティアヌス帝は、疲弊した広大な国土を一人で統治することは困難であるとして、まず帝国を二分割し、二人の皇帝を定め、一人ずつ配置した。更に分割された領土を二分割し、それぞれ正帝と副帝を配置した。この四分割統治は、テトラルキアと呼ばれる。
AD.312 コンスタンティヌス一世による再統一
四分割された領土は、継承権を巡り分裂するが、コンスタンティヌス一世により再統一された。
しかしその死後、継承権を巡り再び分裂する。
AD.375 ゲルマン人大移動
ゲルマン民族の、移住目的の大移動が始まる。
これに対し、東ローマ正帝テオドシウス一世は移住を容認し、更に移住費用をも負担し、逆手にとって帝国防衛の任務を委ねた。
国の根幹である3K労働(国防)は、外国人労働者に委ねられた。
AD.394 フリギドゥスの戦い
東ローマ帝国正帝テオドシウス、西ローマ正帝エウゲニウスを破る。
これにより、帝国は再統一された。
この戦いに於いて、二万の西ゴート族を率いるアラリックがテオドシウスを支援した。しかし一万の犠牲を払いながらも僅かな見返りしか得られず、ローマ軍の旗下を離れる。
この年、テオドシウス死去。帝国は再び東西に分割され、東は長男のアルカディウス(18)に、西は次男のホノリウス(10)に託された。
テオドシウスは、幼い二人の後見人として、皇帝護衛隊長のスティリコを指名。養女セレーネ(弟の娘)を嫁がせ、ローマ軍総司令官(マシステル・トリウスクエ・ミリティアエ)に任命していた。
スティリコの父はテオドシウスの下で出世したゲルマン系ヴァンダル人、母はローマ人。
アルカディウスが東ローマ帝国を継承した時、実権は宦官のルフィヌスに握られていた。彼は既得権益を守る為、スティリコの排除を画策する。
AD.395 アラリックの侵攻
ローマ軍を離れたアラリックは西ゴート王に選ばれ、正当な報酬と権利を求め、首都コンスタンティノープルへ向け進軍を開始した。
スティリコはこれを破るが、ルフィヌスはスティリコに対し反乱の嫌疑を掛け、アルカディウスを通じて、軍を解散し兵をコンスタンティノープルに送るよう勅書を出す。
スティリコは、「臆病なあの馬鹿者の仕業だ」と一括し、軍団を腹心のガイナスに預け、自らコンスタンティノープルへ赴いた。
コンスタンティノープルに到着すると、その閲兵式に於いて、軍団の憎悪に囲まれたルフィヌスは殺害された。
スティリコの指示に依るかは不明である。結果として実権は皇后アエシア・エウドクシアと宦官エウトロピウスへと移り、軍団は解散させられた。
軍団不在の状況で、アラリックは進路をギリシャに変更し、略奪を開始する。
彼の行動パターンは決まっており、要求が通らない場合は、略奪でそれに応える。軍団が解散させられたことを知らずに、勝てないと判断した為略奪へと方針を変えたのではなかろうか。まさかこの状況で軍団が解散させられるなど、信じようもない。
宦官エウトロピウスは解散させられた軍団に対し、首都防衛を指示する。
スティリコはこれを無視し、ギリシャの救援に駆けつけアラリックを破る。しかし、アラリックを捕えることが出来ず、同じ蛮族の血を持つ者に忖度したと讒言され、再び軍は解散させられた。
その機に乗じ、アラリックはコンスタンティノープルへと向けて進軍を再開する。
これに対し、宦官エウトロピウスは、アラリックを「イリリクム軍司令官」に任命し、アラリックの要求に応えた。イリリクムとは、イタリアとギリシャを繋ぐ地方である。
正規軍はガイナスの指揮下に入り、スティリコは事実上、東ローマ帝国から追放された。
AD.398 ギルドーの乱
時は遡りAD.325、キリスト教を公認し、国家統合の理念に組み込もうと考えていたコンスタンティヌス一世にとって、理念によるキリスト教の分裂は、解決すべき問題であった。
最も厄介な問題は、反体制的な、殉教に対する信奉である。信仰を曲げる行為を批判し、殉教を賛美する姿勢を崩さぬ厳格主義者達は、穏健派と対立し、両者はキリスト教世界を二分していた。
コンスタンティヌス一世はこの問題に介入し、教会の問題を、司教達による公会議に於いて解決する事を決定する。以後、キリスト教世界に於いて、公会議による正統の峻別が進められていく。
AD.313、ローマの公会議に於いて、厳格主義者を代表するドナトゥス派は退けられ、穏健派を代表するカエリキアヌス派が認められた。
ドナトゥス派は、その理念から来る必然として、当然この決定を受け入れなかった。
コンスタンティヌス一世は、再三説得を試みるが、当然受け入れられない。そして最終的に弾圧を試みた。これは、公権力による初めての異端弾圧であった。しかしそれ故、コンスタンティヌス一世は躊躇いを隠せず、AD.321、弾圧を中止し、彼等の処遇を「神の裁きに任せる」とした。
以後ドナトゥス派は北アフリカに於いて一大勢力を築き、ローマから認められた正統派カトリックのカルタゴ教会と対立を深めていくことになる。そして、少数の特権階級の支持するカトリック対、多数の貧困層の支持するドナトゥス派という構図が形成されていく。
そしてその対立を利用して、北アフリカに独自の勢力を築こうとする者が現れた。
AD397、テオドシウス一世により「アフリカ担当軍司令官」に任命されていたムーア人、ジルドは、ドナトゥス派の反ローマ感情を煽り、西ローマを脱し東ローマ皇帝アルカディウスへの忠誠を誓うことを宣言した。更には、西ローマであるイタリアへの食料の禁輸を断行する。これにより、東西ローマ帝国の分断は促進され、地政学的に西ローマ帝国を、カルタゴと東ローマ帝国で挟むことになり、カルタゴに対する軍事的支援を東ローマから引き出すことが期待出来る。
参考
https://ja.wikipedia.org/wiki/カラカラ
https://ja.wikipedia.org/wiki/アントニヌス勅令
https://ja.wikipedia.org/wiki/ディオクレティアヌス
https://ja.wikipedia.org/wiki/コンスタンティヌス1世
https://ja.wikipedia.org/wiki/テオドシウス1世
https://ja.wikipedia.org/wiki/フリギドゥスの戦い
https://ja.wikipedia.org/wiki/アラリック1世
https://ja.wikipedia.org/wiki/コンスタンティヌス1世#ドナトゥス派問題
私見
後日更新

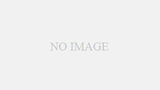
コメント