中国共産党による、組織中枢部に対する賄賂及びハニートラップは、ある種の異彩を放つ脅威として認識されている。
この脅威、実は紀元前に成立したとされる兵法書にそのまま書かれている。
「六韜」である。
脅威から免れるには、まず脅威を知らねばならない。
脅威の真相を知れば、意外にも、扱いやすい相手として現れるものである。
・・・
B.C.1,000年頃、中原(黄河流域)を支配していたのは商(殷)という名の国であった。
その国の最後の帝は帝辛(殷の帝名は、帝と十干の組み合わせ、個人名は受、蔑称は紂王)と呼ばれた。
彼の政は残虐非道とされ、関中を支配する周の武王を盟主とした、連合軍によって滅ぼされた。
これを「牧野の戦い」という。
この戦いで第一功とされたのが、太公望と呼ばれた、羌族出身の人物である。
羌族は、商により生け贄として狩られていた民族であった。
彼は山東を支配する斉の国に封じられ、姜斉(斉は後に田氏に乗っ取られ、田斉となる)の始祖となる。
この太公望と文王(武王の父)、そして太公望と武王の対話形式で描かれる、国家運営に於ける戦略及び戦術に関する問答が、「六韜」である。
成立年代は不詳である。中華最古の兵法書であるかもしれないし、そうではないかもしれない。仮説は幾度となく覆されてきた。
・・・
「六韜」は、六つの韜(武器の収納袋)から成り立つ。
答えは武韜文伐篇にあるが、それを読んだだけでは只唖然とさせられるだけであろう。
六韜全体の思想に位置付ける事により、これを逆手に取ることが可能となる。
文韜
文師篇
人心を捉え、天下を帰服させる方策を問う。
「人はその禄を食みて、すなわち君に服す。」
「嗚呼、曼曼緜緜(枝葉の生い茂った様から転じて、人材の豊富な様)たるもその聚(人の集まり)必ず散ず。」
「天下の利を同じくする者は、即ち天下を得、天下の利を擅にするする者は、則ち天下を失う」
天下万民の利益を己の利益と見做し、それを保障せぬ限り、人心は離れる。
盈虚篇
実例として帝堯の政を問う。
「心を削り志を約し、事に無為に従う。」
天下万民と心を一つにするということは、己の意図に従わず、成るべくして成るところのものに従い正すということ。
国務篇
君主が愛され、民が楽しむ政を問う。
「善く国を為むる者は、民を馭すること父母の子を愛するが如く、兄の弟を愛するが如し。」
天下万民に愛されるには、天下万民を家族のように愛さねばならぬ。
大礼篇
君臣の礼について問う。
「周き(周く知らしめす者:君)は天に則るなり。定る(役割を定められた者:臣)は地に則るなり。」
「天下の目を以て視れば、則ち見ざるなし。天下の耳を以て聴けば、則ち聞かざるなし。天下の心を以て慮れば、則ち知らざるなし。輻輳して(車軸に矢が集まるようにインテリジェンスを纏め上げる)並び進めば、則ち明(視野)蔽われず。」
地は皆異なるが、同じ一つの天を戴く。同様に、君主は臣下に対し公明正大な同一の存在として君臨することで、臣下を通じ、全方位に対応せねばならない。
明伝篇
栄枯盛衰の理由を問う。
「義、欲に勝てば則ち昌え、欲、義に勝てば則ち滅ぶ。」
私欲を捨てねば滅びる。
六守篇
君主が地位を失う理由を問う。
「六守長ずれば則ち君昌え、三宝全ければ則ち国安し。」
仁(人を人として慈しむ事)、義(同胞を同胞として慈しむ事)、忠(真心を尽くす事)、信(誓言を守る事)、勇(困難を前にして逃げぬ事)、謀(あらゆる事態に困窮せぬ事)の六守と、農、工、商の三宝を失えば、君主は地位を失う。
守土篇
領土を守る方策を問う。
「天は四時を生じ、地は万物を生ず。」
「聖人はこれに配し、以て天地の経紀となす。」
国土を守るには、風土に応じ、過不足無く調和を守ること。
上賢篇
人材登用を問う。
「それ王者の道は、竜首の如く、高く居りて遠く望み、深く視て審らかに聴き、その形を示し、その情を隠し、天の高くして極むべからざるが若く、淵の深くして測るべからざるが若し。」
天下万民の実状を明察しながら、己の意図を知られてはならない。
臣下が「己(君主の私)」ではなく「天下万民」の意を汲む様に計らい、その意図する処を理解する者を採用するのが良い。
挙賢篇
賢臣の登用が困難である事の理由を問う。
「君、世俗の誉むる所の者を以て賢となし、世俗の毀る所の者を以て不肖となせば、則ち党多き者は進み、党少なき者は退く。是の若くなれば、則ち群邪比周(邪な連中が徒党を組み)して賢を蔽い、忠臣は罪なきに死し、姦臣は虚誉を以て爵位を取る。」
臣下が「己(君主の私)」に拘泥することを妨げねば、真の賢臣を登用することは出来ない。
賞罰篇
効率的な勧善懲悪を問う。
「賞信罰必、耳目の聞見する所に於いてすれば、則ち聞見せざる所の者も、陰に化せざるはなし。それ誠は天地に暢び、神明に通ず。而るを況んや人に於いてをや。」
必ずそうなると判っていれば、皆それに従う。故に、信義は守り通さねばならない。
兵道篇
用兵を問う。
「およそ兵の道は一に過ぎたるはなし。一とは能く独り往き独り来たるなり。」
「聖王は兵を号じて凶器となし、已むを得ずじてこれを用う。」
「兵勝の術は、密かに敵人の機を察して、速やかにその利に乗じ、復た疾くその不意を撃つ。」
用兵の王道は軍を一つに纏め上げる事である。しかし、古の聖王は兵を不肖の器と見做し、已むを得ぬ時にのみこれを用いた。已むを得ずこれを用いる時は、敵の弱点を察し速やかにその不意を突くことである。
武韜
発啓篇
殷の紂王を伐つ事を問う。
「全勝は闘わず、大兵は創つくなし。」
「天下を利する者は、天下これを啓き、天下を害する者は、天下これを閉ず。天下は一人の天下に非ず、すなわち天下の天下なり。」
「民に取るなき者は、民これを利す。国を取るなき者は、国これを利す。天下を取るなき者は、天下これを利す。」
最も理想的な勝利は、戦わずして勝つことである。己ではなく天下の求めるものを保障する者に、自ずから天下は下る。
文啓篇
聖人の政を問う。
「聖人はこれを静にせんと務め、賢人はこれを正さんと務む。愚人は正しくする能わず。故に人と争う。」
「天に常形あり、民に常生あり。天下とその生を共にして天下静かなり。太上はこれに因り、その次はこれを化す。それ民化して政に従う。ここを天は為すなくして事を成し、民は与うるなくして自ずから富む。これ聖人の徳なり。」
まずは当り前の事を守らせ、それが出来てから多少の軌道修正を行う。特別何かを意図して事を起こさなくても、自ずから改善されるのを補佐するだけで良い。
文伐篇
文伐(文韜を理解した上で、武力を用いず征伐する事)を問う。
「一に曰く、その喜ぶ所に因って以てその志に順う。」(e.g.米中国交正常化)
「二に曰く、その愛する所(寵臣)に親しみ(接近し)て、以てその威を分かつ(勢力を二分する)。」(e.g.親中派と反中派の対立)
「三に曰く、陰かに左右(近臣)に賂い(賄賂を贈る)、情を得ること甚だ深く、身は内にして情は外にす。」(e.g.習近平来日擁護)
「四に曰く、その淫楽(淫らな楽しみ)を輔けて、以てその志を広くし(情欲を募らせ)、厚く珠玉を賂い(宝玉を贈り)、娯ましむるに美人を以てし(美女を献上し)、辞を卑くし(謙ってものを言い)聴くに委い(調子を合わせて話を聞き)、命に順いて合す(同調する)。」(e.g.ハニートラップ)
「五に曰く、その忠臣を厳にして(祖霊を祭るかの様に盛大にもてなす)、その賂いを薄くし(君主への賄賂は減らし)、その使いを稽留してして(留め置き)、その事を聴くなかれ(伝言の中身を聞かずに放置する)。亟かに代わりを置くことを為さしめ(代理を送らせ)、遺る(代わりの使者)に誠事(誠意でもてなす)を以てし、親しみてこれを信ぜば(親しく接し、信用しているかの様に見せかければ)、その君まさに復たこれに合わんとす(再びこちらに歩調を合わせてくる)。」(前の使者を疑わせ、後の使者を信用させる事で、分断を謀る。)(有能な人物との外交交渉には応じず、無能な人物との交渉を成功させ、無能で籠絡しやすい人物を敵国の英雄として祭り上げさせ、無自覚なスパイを獲得する。e.g.中国とのパイプを持つと自覚する人物の多く。)
「六に曰く、その内(国内の重臣)を収め(買収し)、その外(在外の重臣)を間し(離間させ)、才臣(才ある重臣)、外に相け(他国の国益を守り)、敵国、内に侵さば、国滅びざること鮮し。」(e.g.親中派)
「七に曰く、その心を錮せん(塞ぎ込ませる)と欲せば、必ず厚くこれに賂い(賄賂を贈り)、その左右(側近)の忠愛(忠臣や寵臣)を収め(買収し)、陰に示す(誘導する)に利(私利を貪ること)を以てし、これをして業(職責)を軽んじ(怠り)、蓄積(国の備蓄)を空虚ならしむ。」
「八に曰く、賂うに重宝を以てし、因ってこれ(敵国の君主)と謀り(謀を企て)、謀りてこれを利す(利益を得させる)。これを利すれば必ず信ぜん(信じるであろう)。これを重親と謂う。重親を積まば(繰り返せば)、必ず我が用を為す(こちらの意向に応ずる様になる)。国を有ちて外にせば(守るべき国を持ちながら、他国を優先する様であれば)、その地必ず敗れん。」(e.g.習近平来日擁護)
「九に曰く、これを尊ぶに名を以てし(その名を称え)、その身を難すなく(国(=君主)を脅かすことなく)、示す(誘導する)に大勢を以てす(威勢が広大であると吹聴する)。これに従わば必ず信ぜん。その大尊を致して(尊大さを極め)、先ずこれが栄を為し(国庫を浪費して自らを飾り立て)、微かに聖人を飾らば(密かに聖人を気取るならば)、国すなわち大いに偸らん(皆驕り高ぶり自らの責務を怠るであろう)。」(e.g.AIIBによる巨額投資と、汚職蔓延、及び返済不能による国土割譲、外交従属)
「十に曰く、これに下るに必ず信ありて(必ず信用を得て臣従し)、以てその情を得(心を掴み)、意を承け事に応じ(意のままに応じ)、与に生を同じくするが如くす(兄弟の様に接する)。既に以てこれを得(寵臣の地位を得た後)、及びて微にこれを収む(他の寵臣を買収する)。時まさに至らんとするに及びて(時至りて)、天これを喪すが若し(運命であるかの様に滅びる)。」(e.g.米中国交正常化からトランプ大統領就任までの米国。日中国交正常化後の日本(現在進行中))
「十一に曰く、これを塞ぐに道を以てす(敵国を封じるのに、当り前の道理を活用する)。人臣、貴と富とを重んじ、危と咎とを悪まざるなし。陰に大尊を示して(密かに増長を促し)微に重宝を輸り(密かに賄賂を輸送し)、その豪傑を収め(買収し)、内に積むこと甚だ厚くして(自国に膨大な備蓄を蓄えていたとしても)、外には乏しきを為し(敵国には資財が欠乏しているかの様に見せかけ)、陰に智士を内れて(密かにスパイを送り)、その計を図らしめ(敵国の政に参画させ)、勇士を内れてその気を高からしむ(兵を贈り士気を上げさせる)。富貴甚だ足りて(富める者を満たしてやり)、常に繁滋あれば(豊かな生活を保障してやれば)、徒党すでに具わる(内応する勢力が出現する)。これこれを塞ぐと謂う。国を有ちて塞がるれば、安くんぞ能く国を有たん。」
「十二に曰く、その乱臣を養いて以てこれを迷わし(乱臣に餌を投下し政を混乱させ)、美女淫声を進めて以てこれを惑わし(淫靡な歌舞音曲に溺れさせ)、良犬馬を遺りて以てこれを労らす(趣味に没頭させる)。時に大勢を与えて以てこれを誘い(増長させて油断を誘い)、上察して天下と与にこれを図る。(陛下は時が来た事を察して、他の同盟国と共に、天下の意思としての大義を示し、討伐を図るのです)」
「十二節備わりて、すなわち武事を成す。所謂上は天を察し、下は地を察し、徴すでに見れて、すなわちこれを伐つ。」
順啓篇
天下に向き合う姿勢を問う。
「天下は一人の天下に非ず、唯だ有道者のみこれに処る。」
天下を己の私物と見做してはならない。
三疑篇
強敵への攻め方、離間の策、分断の策を問う。
「およそ謀の道は、周密(周く秘密とする)を宝となす。」
「その強を攻むるには、必ずこれを養いて強からしめ、これを益して張らしむ。太だ強ければ必ず折れ(強すぎる軍は反乱を起こす)、太だ張れば必ず欠く(過剰な富は汚職を蔓延させる)。」
「その親(君臣の親密な関係)を離さんと欲すれば、その愛する所とその寵人とに因りて(使って)、これ(君主)に欲する所を与え、これに利する所を示し(利益誘導し)、因って以て(その様にした上で)これを疎んじて(遠ざけて)、志(今まで得てきた利益)を得しむるなかれ(得られない様にしてしまえ)。彼、利を貪りて甚だ喜べば(これまでの利益を大いに貪り喜んでいたならば)、疑いを遺してすなわち止む(寵愛する者に対する猜疑心を残して、その関係は終るであろう)。」
「これを淫(淫蕩に耽らせる)するに色(美女)を以てし、これに啗すに利を以てし(利益に目を眩ませ)、これを養うに味を以てし(美食に放蕩させ)、これを娯ましむるに楽をもってす(娯楽に現を抜かさせる)。すでにその親を離し(離間を成立させた上で)、必ず民を遠ざけしめて、謀を知らしむるなかれ。扶けてこれを納れ、その意を覚らしむるなく、然る後に成るべし(成就するはずである)。」
竜韜
王翼篇
軍の運用について問う。
「およそ兵を挙げ師(軍)を師いるに、将(将軍)を以て命となす(命運は委ねられる)。命は通達(諸兵個人の性格から軍全体の戦略に至るまで詳細に通じ、熟達している事)に在り。一術を守らず(固定的な戦術に拘らず)、能に因って職を授け、各長ずる所を取り、時に随って変化し、以て綱紀となす(以上を心に刻め)。故に将、股肱(手足から転じて補佐)羽翼(鳥の羽から転じて補佐)七十二人(太陰暦より。一候は五日、三候は一気、六候は一月、七十二候は一年。)ありて、以て天道に応ず。数を備うること法の如くし(胡散臭いと思わず、とにかくこの様にして数を厳格に揃え)、審らかに命理を知り(見かけは胡散臭いが、その内容はきちんと理屈を通しているから、そこの所をよく理解して)、能を殊にし(能力に応じて特殊な任に当らせ)技を異にして(技能に応じて異なる部署に配属し)、万事畢わる。」
六韜の戦術は、諸個人の得意分野を最大限に発揮することに重きを置いており、それはつまり適材適所とも言えるが、得意分野は千差万別である為、それを整理する為のカテゴリーとして、便宜的に七十二という数字を使っている。内容の合理性と、その合理性の特殊性は、以下述べられる具体的な将の配置を紐解くことで明らかとなる。
「腹心一人、謀(戦略)を賛け卒(生命を脅かす状況)に応じ、天を揆り(天候に多大な影響を受ける経済の動向を正確に把握し)変を消し(異変を解消し)、計謀を総覧し、民命を保全するを主る。」
戦略と危機対応を統括する腹心を一人。守るべき対象は、君主ではなく万民である事に留意。
「謀士五人。安危を図り(安全なのか危険なのかを予測し)、未萌を慮り(事態の表面化を未然に防ぐよう配慮し)、行能を論じ(臣下の功績と能力を評価し)、賞罰を明らかにし、官位を授け、嫌疑を決し、可否を定むるを司る。」
安全保障と論功行賞と司法を司る謀士を五人。この三者の関係性は以下の観点から結びつけられる。
人事は、安全保障の観点から位置付けられねばならない。
それは、特定の縁故、特定の派閥、一方的な善悪、刹那的利益等を忖度する観点では無く、天下万民の総合安全保障である。
「天文三人、星暦(星の運行)を司り、風気(気候)を候い、時日(期日)を推し、符験(吉凶の兆し)を考え、災異を校り、天心(天の御心)去就の機を知ることを司る。」
ベストなタイミングを天の恩寵と思わせ、士気を上げる戦術を司る天文を三人。
「地利三人、軍の(行軍や駐屯)の形勢、利害の消息、遠近険易、水涸山阻、地の利を失わざるを主る。」
地理を利用した戦術を司る地利を三人。
「兵法九人、異同(意見の相違)を講論し、成敗(裁定)を行事し(下し)、兵器を簡錬し(選定、鍛錬し)、非法(方針に反する行為)を指挙(検挙)するを主る。」
戦略に法り、戦術を収斂し、方針に則り兵を統率する兵法を九人。
「通糧四人、飲食を度り、蓄積を備え、糧道を通じ、五穀を致し、三軍(左翼、中軍、右翼を合わせた全軍)をして困乏せざらしむるを主る。」
兵站を司る通糧を四人。
「奮威四人、才力を択び(有能な兵を選抜し)、兵革(戦場に於ける分岐点)を論じ、風馳電掣(風の如く駆け、稲妻の如く制圧する)、由る所を知らざらしむるを主る。」
遊撃を司る奮威を四人。
「伏旗鼓三人、旗鼓(自軍の旗や信号用の太鼓)を伏せ、耳目を明らかにし、符印(割符)を詭り、号令を謬り、闇忽として(闇に紛れ何食わぬ顔で)往来し、出入すること神の若くなるを主る。」
工作活動を司る伏旗鼓を三人。
「股肱四人、重きに任じ難きを持し(最終防衛ラインの守りを固める重責と難問を担当し)、溝塹(堀や塹壕)を修め、壁塁(城壁や土塁)を治め、以て守禦に備うるを主る。」
本陣防衛を司る股肱を四人。
「通才二人、遺を拾い(残された問題を拾い上げ)過を補い(過ちを補い)、賓客に応偶し、論議談語し、患を消し(表面化した問題を解消し)結を解く(問題の根源を紐解く)を主る。」
外部の情報を採り入れ客観的に分析する、シンクタンクを司る通才を二人。
「権士三人、奇譎(奇計案出)を行い、殊異(特殊部隊)を設け、人の識る所に非ずして(悟られずに)、無窮の変を行う(情勢変化の主導権を握り続ける)を主る。」
奇計を司る権士を三人。
「耳目七人、往来して言を聴き変を視、四方の事、軍中の情を覧るを主る。」
インテリジェンスを司る耳目を七人。
「爪牙五人、威武を揚げ、三軍を激励し、難を冒し(難所を攻略し)鋭を攻めて(強敵を攻め)、疑慮する(怯えて蹲る)所なからしむるを主る。」
斬込み隊を司る爪牙を五人。
「羽翼四人、名誉(武名)を揚げ、遠方を震わし、四境を動かし、以て敵の心を弱くするを主る。」
豪傑(名を聞いただけで脅かす猛者)四人。
「遊士八人、姦(倫理的乱れ)を伺い変(誓約の乱れ)を候い、人情を開闔し(人心を操り)、敵の意を観て(敵の意図を探り)、以て間諜(スパイ活動)を為すを主る。」
スパイ活動(実質文伐)を司る遊士を八人。
「術士二人、譎詐(偽り)を為し、鬼神に依託し(仮託し)、以て衆の心を惑わすを主る。」
妖術師を詐称し民心を惑わす術士を二人。
「方士三人、百薬(あらゆる薬)、以て金瘡(武器による傷)を治め、以て万病(あらゆる病)を痊す(癒す)を主る。」
医療を司る方士を三人。
「法算二人、三軍の営塁糧食(陣の運営及び食糧補給)、財用(必要物資)の出入を会計するを主る。」
財務を司る法算を二人。
以上七十二名。
要約すると、
戦略担当、
戦略補佐、
時期戦術担当、
地理戦術担当(以上二担当部署により、総合戦術が決定される)、
個別戦術管理担当(これ以下個別戦術)、
兵站担当(個別戦術の筆頭に兵站が挙げられる事に留意)、
遊撃担当(戦闘部隊の筆頭に遊撃隊が挙げられる事に留意 アレクサンダーの必勝パターンを参照されたし)、
工作担当(偵察と情報攪乱による敵の弱体化 戦闘中の情報攪乱は、決定的な役割を果たす)、
防衛担当(防衛がこの位置に置かれていることから、攻撃を優先させていることが覗える)、
シンクタンク担当(全体把握 戦略に関わる情報の収集と解析 以下、総合戦術から逸脱した状況を想定している)、
奇計担当(特殊な状況をカバー)、
インテリジェンス担当(状況把握 戦術に関わる情報の収集と解析 戦闘中の状況把握は、現代と違いリアルタイムで行えない為、補助的な役割に留まる)、
斬込み隊担当(劣勢打開 苦肉の策か)、
豪傑担当(威圧 武名は三国志演義ほど実世界では役には立たない)、
スパイ担当(実質的に文伐に相当 配置から下策と見做されていることが覗える)、
妖言担当(敵の発狂を狙う 戦術最下位の下策)、
医療担当(以下、戦力外二部隊)、
財務担当
論将篇
将の条件を問う。
「将に五材十過あり。」
「所謂五材とは、勇智仁信忠なり。勇なれば則ち犯すべからず(攻め込まれない)。智なれば則ち乱すべからず(混乱しない)。仁なれば則ち人を愛す(部下をいたわる)。信なれば則ち欺かず(嘘を言わない)。忠なれば則ち二心なし(裏切らない)。」
「所謂十過とは、勇にして死を軽んずる者あり(「暴すべきなり(そんな奴は挑発してその本性を曝け出させちまいな)」)。急にして(短気で)心速やかなる(せっかちな)者あり(「久しくすべきなり(そんな奴は持久戦に持ち込み苛つかせときな)」)。貪(貪欲)にして利を好む者あり(「賂うべきなり(そんな奴には賄賂を贈っとけ)」)。仁にして(優しすぎて)人に忍びざる(黙ってみていられない)者あり(「労すべきなり(そんな奴には心配事を山ほど贈っとけ)」)。智にして心怯なる(臆病な)者あり(「窘むべきなり(そんな奴は袋小路に追い込んでやれ)」)。信にして喜んで人を信ずる者あり(「誑くべきなり(そんな奴にはたんまり嘘を贈って発狂させちまいな)」)。廉潔にして(清廉潔白に固執し)人を愛せざる(相手の事情を全く考慮出来ない)者あり(「侮るべきなり(そんな奴は侮辱するだけで部下に当たり散らして裏切られるだろう)」)。智にして心緩なる(のんびりした)者あり(「襲うべきなり(そんな鈍くさい奴には奇襲をかけな)」)。剛毅にして(剛直で自信過剰な為)自ら用うる(自分で何でもやってしまう)者あり(「事とすべきなり(そんな奴には山盛りの仕事をご褒美しちまいな)」)。懦(怠惰)にして喜んで人に任ずる(人任せにする)者あり(「欺くべきなり(そんな奴は現状を何も判っちゃいねーだろうから余裕で欺せるな)」)。」
士気を保ち、状況を的確に把握し、部下に慕われ、情報伝達が正確であり、裏切らない将を理想とする。
逆に、そのバランスの崩れた将は、容易く手取られる。
中国思想は、状況に応じた的確なバランスを重視し、このバランスの取れた状態を、中庸、又は道と表現する。これは、西洋哲学に於ける形相やイデアに相当する、根本原理と言える。
選将篇
人選を問う。
「これ(相手の本質)を知るに八徴(八つの徴候)あり。」
「一に曰く、これに問うに言(直接論旨を明確に言う)を以てし、以てその詳(問いかけに対する反応)を観る。」
「二に曰く、これを窮する(窮地に陥らす)に辞(乱れた糸を解きほぐす様に詳細を追究する)を以てし、以てその変(取り乱す様)を観る。」
「三に曰く、これに間諜(スパイ)を与えて(遣わし)、以てその誠(事実、その為す所)を観る。」
「四に曰く、明白に顕問(本心を顕して問い:腹を割って問いかけ)して、以てその徳(日常の人柄:本来の人柄)を観る。」
「五に曰く、これを使う(任用する)に財(財務)を以てし、以てその廉(末席を潔しとする様:清廉な様)を観る。」
「六に曰く、これを試すに色(美女)を以てし、以てその貞(神聖不可侵な様)を観る。」
「七に曰く、これに告ぐるに難(難題)を以てし、以てその勇(意気揚々と取り組む様)を観る。」
「八に曰く、これを酔わすに酒を以てし、以てその態(内心の顕現)を観る。」
普通に問いかけた後、詰問し追い詰め、不満を抱いたであろう所を、間諜を遣わし、本心を探り、確かな人物であれば、本心を打ち明け腹を割って話し、信用出来るようであれば、先ず財務を任せ、色恋沙汰に現を抜かし流用する様なことも無ければ、更に難題を与え、意気揚々とそれをこなす様であれば、最高のパートナーであるか、あるいは最悪のスパイである。酒の付き合いを深め、その本心を確かめねばなるまい。
立将篇
任命時の儀礼を問う。
「およそ国に難あれば、君、正殿を避け(別殿に於いて)、将を召してこれに詔して曰く、社稷(土地の神と穀物の神:国土)の安危は、一に(ひとえに)将軍に在り。今、某国不臣なり(臣下の道に背く)。願わくは将軍、師を師いてこれに応ぜよ、と。」
権限委譲を正殿ではなく別殿にて行うことで、主権の不可侵性を演出する。
「将すでに命を受くれば、すなわち太史(天文、暦、国史を司る官職)に命じて卜せしむ(亀卜させる)。斎すること(斎戒すること)三日、大廟(祖廟)に之き、霊亀を鑽り(亀甲に錐で穴を開け、そこに焼けた棒を差し込み、ひび割れを診て占う)、吉日を卜して、以て斧鉞(斧と鉞)を授く。」
実質的には、号令を掛けて準備を進め、士気を高めていく期間を設ける。
「君、廟門に入り、西面して立つ。将、廟門に入り、北面して立つ。」
廟堂に正面に向く将が主役であり、西に向く君主は脇役である。但し、西面に意味を見出すとすれば、それは天体の運行が東から西へと移動する為、昇る天を背景に、天意により権限を委譲するという意味を想起させる為であろうか。
「君親しく鉞を操り、首を持ちて(刃の方を持って)将にその柄を授けて(柄を握らせて)曰く、これより上、天に至るまで、将軍これを制せよ(剪定せよ:秩序を正せ)、と。復た斧を操り柄を持ちて(柄を握り)、将にその刃を授けて(刃の方を持たせて)曰く、これより下、淵(地の底)に至るまで、将軍これを制せよ。」
鉞は、射程を広げ敵を攻撃する為の人殺しの武器。斧は、裁定を下す王の武器。敵を征伐する権限は全て委譲するが、最終的な裁定権は、主権を握る君主の掌中に在る事が確認される。
「その虚(敵の隙)を見れば則ち進み、その実(敵の充実)を見れば則ち止まれ。三軍(左軍、中軍、右軍を合わせた全軍)を以て衆となして(大軍を頼りにして)敵を軽んずるなかれ。命を受くるを以て重しとなして(重責を忘れず自重し)死を必するなかれ(死を覚悟せねばならぬ様な事は避けよ)。身貴きを以て人を賤しむなかれ(地位などに説得力はない)。独見を以てして衆に違うなかれ(皆の同意を得て一致団結せよ)。弁説を以て必然とするなかれ(空論に踊らされるな)。士(士官に相当)いまだ坐せざれば、坐すなかれ。士いまだ食わざれば、食うなかれ。寒暑必ず同じくせよ(苦難を必ず分かち合え)。此の如くば、士衆(上は士官から下は兵卒に至るまで)必ず死力を尽くさん、と。」
この節は、不思議なほど近代的であり、愛情に満ちている。根底には「生きて帰れ」という願いが通底しており、それは将のみではなく全軍に向けられたものであり、その為に、平等と団結が謳われる。
穿った見方をして、身方を死なせて生き残る為の策謀に過ぎないという意見も出てくるかとは思うが、その見方は、少々問題があろうかと思われる。
六韜には、二つの視点が分離している。
文韜に於いて、天下万民の視点が謳われる。
これに対し、その視点とは真逆の、文伐に代表される、天下万民を虐げる視点が謳われる。
本意は前者にあり、後者は反面教師を詳細に描いているに過ぎない。
自軍に向けられた視線は、当然前者の視点を前提とする。
後者の視点に飲み込まれる者は俗物であり、身内にその視線を向け、内側から蝕まれ、軈て自壊する。
「将すでに命を受け(君命を受諾した後)、拝して(拝謁して)君に報じて曰く、臣聞く、国は外より治むべからず(国外からでは、国内の統治はままならない)。軍は中より(同様に、外征中の軍を、中央の指示で)御すべからず(制御してはならない)。二心以て(前線に於ける判断と、それを知らぬ中央からの指示の板挟みに遭えば)君に事うべからず(君の要望に応えることは出来ない)。疑志以て(現場に即応せぬ指示に、疑念を持ちながら)敵に応ずべからず(敵に対応してはならない)、と。臣すでに命を受け、斧鉞の威を専らにす(軍の全権を賜りました)。臣敢て生きて還らじ(生還は出来ぬものと覚悟しております)。君亦た一言の命を臣に垂れよ(後一言、軍権に干渉せぬよう、詔を賜りたい)。君、臣に許さずんば(お許し頂かぬのであれば)、臣敢て将たらじ(君命を辞退させて頂く)、と。君これを許す。すなわち辞して(謝辞を示して)行く。軍中の事は君命を聞かず、皆将より出づ。敵に臨み戦いを決し、二心あるなし(戦場に専心するのみ)。此の若くなれば則ち上に天なく、下に地なく、前に敵なく、後に君なし。この故に智者はこれ(将)が為に謀り、勇者はこれ(将)が為に闘う。気、青雲を厲ぎ、疾きこと馳騖(馬が疾走する様)するが若く、兵、刃を接えずして敵降伏す。戦い、外に勝ち、功、内に立つ。吏遷され上賞せられ、百姓歓悦し、将、咎殃(罪過や災い)なし。この故に風雨時節あり、五穀豊登し、社稷安寧なり。」
「武王曰く、『善きかな』」
将威篇
将の威信を保つ方策を問う。
「将は大(位の高い者)を誅する(誅殺する事)を以て威(威信)と為し、小(位の低い者)を賞する(報償する事)を以て明(明察)と為し、罰(罰則が)審らかなる(明白に示される事)を以て禁止(禁止事項)と為して、令(軍令が)行わる(遵守される)。」
ここまでであれば、「法の下の平等により威信を保つ」と解釈出来るが、ここから先は、甚だ勘違いし易い文章が続く。
「故に一人を殺して三軍震う者は(たった一人殺しただけで全軍が恐れ戦くならば)これを殺し、一人を賞して万人説ぶ者は(たった一人を報償するだけで全軍が歓喜に沸くならば)これを賞す。殺すは大を貴び、賞するは小を貴ぶ。その当路(執政に於いて)貴重の人を殺すは、これ刑、上に極まるなり。賞、牛竪(牛飼い)、馬洗、厩養(馬飼い)の徒に及ぶは、これ賞、下に通ずるなり。刑上に極まり、賞下に通ずるは、これ将の威の行わるる所なり。」
ハッキリ申して、これはトラップである。
解釈は、二つの視点により、二つに分かれる。
将が己の目的の為にこの篇を参照する場合、罰を下す者と、賞を与える者を探し始める。
将が天下万民の視点に立つ場合、裁定の厳正さを吟味し始める。
前者が慣例化される場合、法は裁定者の下で形骸化し、裁定者の地位を争う内乱状態が常態化する。
後者が慣例化される場合、法はアイデンティティーと化し、共有する者同士の団結が醸成される。
この分岐は、歴史的に見て極めて重大な意味を持っている。
西欧侵略の東進に対し、清国が防波堤と成り得なかった事実と、大日本帝国が成り得た事実は、ここに起因する。
それぞれ、一例を挙げてみよう。
清国に於いて、林則徐は不当にも罷免された。誰がこの様な政府の下で団結しようなどと思うのであろうか。
これは、守られるべき当路貴重の人が、罰せられた一例である。天下万民の事を思えば、イギリスの不当は明々白々であり、この時点で清国が団結し、徹底抗戦の構えを見せた場合、イギリスの威信は地に堕ちていたであろう事も又、明々白々である。当のイギリス人さえ身方に付けたであろう。その瞬間を目にすることが出来なかったのは、栄耀栄華に固執し、地べたに這いつくばってでも天下万民を思う覚悟が、微塵も無かったからではないのか?
大日本帝国に於いて、北海道に本拠地を置いた旧幕府軍総裁榎本武揚は、陥落直前という状況に於いて、新政府軍に対し、今後の日本に必要なものとして、『海律全書』を贈呈している。新政府軍からは感謝の意と、いずれ翻訳して世に出すとの内容の書状と酒が贈られている。殺し合いをする仲でありながら、お互いの情を理解し合えている。
榎本は意を決し自刃して果てようとするが、近習の大塚霍之丞に抑止され新政府軍に投降した。
軈てその才能を認められ罪を許された榎本は、後に駐露全権大使に就任し、南下を目論むロシアとの間に対等な条約である千島・樺太交換条約を締結し、欧米列強と交わされた不平等条約撤廃の端緒を拓いた。
これは、罰せられるべき当路貴重の人が、天下万民の視点から、許され活躍した一例である。
以上、それぞれ、一例に過ぎない。慣習に基づくものは、無限に湧き出る。
ともかく、六韜という書物は、己に固執する人物を自滅させ、公を重んずる人物には自戒の念を喚起させる、甚だ物騒な書物である。
励軍篇
士気過剰の軍を得る方策を問う。
「将に三勝あり(勝利を得る三つの道がある)。」
「将は冬に裘(毛皮の服)を服せず(着ず)、夏に扇を操らず、雨に傘を張らず。名づけて礼将と曰う。将身ずから礼に服さざれば、以て士卒の寒暑を知るなし。」
「隘塞(険阻な道)を出で、泥塗(泥沼の地)を犯すに(行軍するに及び)、将必ず先ず下りて歩む。名づけて力将と曰う。将身ずから力に服さざれば、以て士卒の労苦を知るなし。」
「軍皆次(宿泊先)を定めて、将すなわち舎(宿舎)に就く。炊ぐ者(炊事番)皆熟して(作業を終えて)、将すなわち食に就く。軍、火を挙げざれば(灯火を灯さぬ間は)、将亦た挙げず。名づけて止欲の将と曰う。将身ずから止欲に服さざれば、以て士卒の饑飽(飢えているか満腹なのか)を知るなし。」
「将、寒暑、労苦、饑飽を共にす。故に三軍の衆、鼓声(進軍を命ずる太鼓の合図)を聞けば則ち喜び、金声(退却を命ずる鐘や鉦の合図)を聞けば則ち怒り、高城(高い城壁)深池(深い城堀)、矢石繁く下るも(矢や石が雨の様に降り注いでも)、士先を争いて登り、白刃始めて合うも(軍が激突しようとも)、士先を争いて赴く。士は死を好みて傷を楽しむに非ざるなり。その将、寒暑、饑飽を知ることの審らかにして、労苦を見ることの明らかなるが為なり。」
全軍兵卒に至るまで、将と艱難辛苦を共にするならば、皆将に命を捧げるであろう。
但し彼等は、「死を好みて傷を楽しむに非ざるなり」。
死なせる為の策ではなく、生を分かち合う者達の、生きのびる為の必然を語っているに過ぎない。
陰符篇
情報伝達を問う。
「主と将に陰符(割符)あり、凡そ八等(八種類)。」
陰書篇
より複雑な情報伝達を問う。
「書を分かちて三部となす。」
軍勢篇
用兵の王道を問う。
私見
後日更新

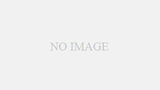
コメント