検察と官邸の関係が問題となっておりますが、そもそも検察とは如何なる実態を持つ組織なのでしょうか。
検察の圧倒的強さと、名目上それを民意により制限する仕組みと、その微妙すぎるバランスについて考えさせられました。
有り難うございます。
警察の仕事
捜査と逮捕。
三権の内、司法に属する。
検察の仕事
刑事裁判を起訴すること。
三権の内、行政に属する。
所属の特別捜査部(特捜)は、例外的に捜査と逮捕を行う。
起訴
被疑者を裁判にかけること。
特別捜査部
政治家汚職、大型脱税、経済事件を独自に捜査する。
検事(副検事)及び検察事務官により構成される。
一般的な刑事事件は警察による捜査及び被疑者の逮捕が行われる。
逮捕権
刑事訴訟法第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
起訴独占主義
起訴は検察官だけが出来る。(例外:検察審査会)
検察審査会
検察官が独占する起訴の権限の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制する為に地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民11人によって構成される機関。
起訴便宜主義
検察官が起訴するか否かを判断する。
起訴率60%
警察が逮捕した被疑者の起訴率は約6割。
有罪率99.9%
検察に起訴された裁判での有罪率は99.9%。
検察官同一体の原則
担当検事から検事総長まで全員が情報を共有。
→ 裁判
→ 三人の裁判官 VS 約百人の検事の総意
→ 検察の総意の勝率
→ 99.9%
法務省と検察庁
検察庁は法務省の特別の機関と呼ばれ、法務省に所属する機関としての印象が強いが、検察庁は法務省の事を「ロジティー」(logistics:兵站:補給部隊)と呼び、逆に道具として扱っている。法務省から優秀な人材を調達し、99.9%の有罪率を維持している。
検察上位の関係性は、検察の出世コースが法務省の事務方のトップである法務事務次官から始まり、東京高検検事長、検事総長へと繋がる事からも覗える。
検察庁と政府
検事総長任命権
内閣は、検事総長を任命する権限を有する。
検察庁法第十五条
検事総長、次長検事及び各種検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
指揮権
総理大臣(法務大臣)が指揮できるのは検事総長のみ。
検察庁法第十四条
法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調べ及び処分については、検事総長のみを指揮する事ができる。
指揮権発動
指揮権を発動することにより、政治家の逮捕を阻止することが可能となる?
検察の抵抗
検察の本流を定める
検事総長就任候補は、検察人事に対する政治介入を牽制する事を目的として、四代先まで決められている。
二年に一人決められる慣例。
検察官の身分保障を利用した、検事総長任命への、検事総長の意向の反映
検察官の身分保障
定年と懲戒免職以外で任を解かれない。
検察庁法第二十五条
検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りではない。
検察庁法第二十二条
検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
検察庁法第二十三条
検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
検察庁法第二十四条
検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となったときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。
検事総長の二年長い定年までの任期を利用した、人事への意向の反映
検事総長の定年は六十五年の誕生日までであり、他の検察官の六十三年よりも二年長い。この2年間に於いて、他の要請による退官は、懲戒免職以外にない。よって、自らの意思により、辞任する日時を自由に決められる。これを利用し、次期検事総長として好ましくないと判断した相手の退官を待って辞任し、他の好ましい人物に検事総長の位を委ねることが可能となる。
私見
法務省に所属しながら行政に属するという捻れた構造の背景を調べてからでないと、何とも言えない。
参考
検察庁法改正に関しては、こちら。

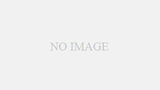
コメント