ウォーレン・バフェット氏が航空株を大量に売却し、それが話題となっております。
彼は、長期的に見て成長するであろう業界に対し、その業界が過小評価されている時に長期投資を行うことで、その業界を支え、利益を生み出してきました。
つまり、彼の投資先を見ることで、長期的に安泰であろう業界を予測出来るのです。
今回彼は、航空株を大量売却しました。
彼は、未来に何を予想して、この様な決断を下したのでしょうか。
現状を俯瞰し直す切掛を頂きました。
有り難う御座います。
ウォーレン・バフェット
バークシャーハサウェイCEO
バークシャーハサウェイ
世界最大の投資会社(ネブラスカ州=バフェットの出身地)
50年間で株価が2万倍に成長。cf.S&P140倍
悪い噂
政府と癒着。
良い噂
・伝統的な投資:良い会社に投資。
・長期投資
「喜んで10年間株を持ち続ける気持ちがないのなら、たった10分でも株を持とうなどと考えるべきですらないのです。」
・巨大な投資を行う流動性がある。
ドル資金 2009年590億ドル → 2020年1,240億ドル
・借入れをしていない。
・不況時に最も打撃を受けている業界に投資。
航空株売却
コロナ不況 → 航空株購入 → 一ヶ月後 → 航空株売却
なぜか
歴史的な政府介入 → 航空業界への大規模な貨幣供給
→ 「今アメリカは、壮大な実験の中にある。」
→ 自由市場が複雑になった。
→ 投資対象の選別に時間をかける必要がある。
私見
時代の流れから「壮大な実験」を位置付けてみる。
経済に焦点を当てるが、経済を、覇権・雰囲気(社会全体の指向性)・経済の三層構造として捉えることにより、簡潔に整理する。
経済だけを見ていると、複雑なこじつけの羅列に終始することになろう。本質的な問題が、その上部構造にある為だ。
第二次大戦後
第二次大戦時、国土を戦場とすることのなかったアメリカには、その国土の広さ、人口の多さ、生産能力の高さを背景に、戦争特需により世界の資金、殊に金が集中した。
第二次大戦後、復興に於ける経済の志向性が、共産主義と資本主義に分裂した。
資本主義を志向する西側陣営では、集積されたアメリカの資本を投資することで、復興が図られた。(ブレトン・ウッズ体制)
この投資は、共産主義を志向する東側陣営に対抗する目的から、各地域の独立と経済成長を約束するものでなければならなかった。(純粋な利潤追求への足枷)
安定した経済成長を図る為、金と交換できる貨幣をドルに限定し、ドルとその他通貨の交換レートを固定した。(金ドル本位制)
成長初期に於いて、アメリカの資本は順当に利益を享受していた。
しかし、各国との技術格差が緩和されるに随い、為替レートが固定されていた為、アメリカ国内の生産コストが相対的に跳ね上がった。
次第にアメリカ経済は、安い外国製品に席巻され、資本流出と景気後退に悩まされ始めることになる。
1960年代
1969 ニクソン、ヴェトナムからの米軍撤退計画を発表
覇権
アメリカ初の敗戦 西側陣営後退
雰囲気
西側陣営の大義に対する疑念 目的の喪失
シャロン・テート殺害事件
第二次世界大戦後、アメリカに於ける長期的な社会の安定は、若者達の国家に対する帰属意識を衰退させ、彼等の視線を保守的なキリスト教的価値観の周縁に位置する文化へと向けていった。そこに在ったのは、白人の圧政に生き生きとして耐え抜いてきた黒人達の文化であった。その文化は、保守的な世代に対し反撥する若者達の感性に共鳴し、「ヴィーガニズム」(人間は動物を搾取することなく生きるべきであるとする思想)へと発展し、「ヒッピー文化」(自然への回帰と一体感の享受を、インド由来の文明を頼りに進めていこうとする動きではあるが、豊かな社会の若者にありがちな、オシャレで手軽な享受の為に、性的倒錯とドラッグへと傾倒していってしまうムーブメント)へと昇華する。その終着点として位置付けられるのが、シャロン・テート殺害事件である。
1969/8/9 ロマン・ポランスキー監督(現在では『戦場のピアニスト』の監督として知られる)と前年に結婚し妊娠中だった、女優のシャロン・テートが、友人達とパーティを楽しんでいる最中に、狂信的なヒッピーの集団に襲われ殺害された。資本主義を享受する富裕層を狙った犯行であっり、シャロン・テートを狙ったものではなく、シャロン・テートである事すら知らなかった。
彼女は「お腹の子供を殺さないで」と嘆願したが、無残にも殺害された。
この事件は、ヒッピー文化の汚点を曝け出すものであり、この事件を契機にこのムーブメントは消滅していく。
残されたのは、アメリカ国民による、アメリカ自身に対する慢性的な嫌悪感であり、その回復は、レーガン政権時代を待たねばならない。
経済
① ドルの信用低下
→ インフレ
② 投資減少
→ 景気後退
1970年代
1972/7/15 ニクソン 訪中宣言
覇権
西側陣営の伸長
雰囲気
『ゴッドファーザー』(1972/7/15公開)
ありふれたものに美が見出される時、それは、既にありふれたものでは無くなっている時であり、ありふれたものに抽象的な意図を見出す時である。この抽象的な意図が大衆に熱狂的に受け入れられる場合、それは、大衆が共通してそれを失っていることを意味し、そして、渇望していることを証明している。
舞台はアメリカ、ニューヨーク。
一代でニューヨーク筆頭のマフィアを築き上げたヴィトー・コルレオーネは、他の有力マフィアであるタッタリア・ファミリーに、麻薬の取引をもちかけられる。しかし、ヴィトーはこれを拒絶する。これに対し、ヴィトーの後継者である息子のソニーが麻薬を扱うことに好意的な姿勢を見せた為、ヴィトーを除けば取引が成立するであろうという憶測を抱かせてしまう。その結果、ヴィトーは襲われ、重傷を負ってしまう。タッタリア・ファミリーの憶測とは異なり、ソニーは激怒し、ファミリー間の抗争が勃発する。そこに、民間に身を置いていたヴィトーのもう一人の息子であるマイケルが加わることで、マイケルを中心に物語は展開していく。
兄のソニーが殺され、妻が爆殺されたマイケルは、父ヴィトーの死を経て、新しいドンに就任する。全ての悲劇が、小さな世界に執着する者たちの小競り合いと下らない陰謀によるものであると気付いたであろうマイケルは、最終的にニューヨークを支配する五大マフィアの全てのドンを抹殺し、唯一のドンとして君臨することになる。曾ては暴力を嫌い、民間に身を置いていたマイケルにとって、それは権力欲に基づくものでは無く、全ての苦悩を自らに背負う、自己犠牲であった。
『ゴッドファーザー』の原作者であるプーヅォは、借金苦の中、渋々この小説を書いている。イタリア系でありながら、マフィアの知り合いが一人もいなかった彼は、ヘミングウェイの小説を参考にし、女手一つで育ててくれた母親を思い出しながら書いた。つまり、完全なフィクションである。
当時コッポラは、未だ一本もヒット作を撮れていなかった。そんな彼に対し、とりあえず低予算でギャング映画を作りたかったパラマウントが目をつける。当初コッポラは、暴力とセックスを売りにした下らない大衆小説として、この申し出を受け付けなかった。しかし再度申し出を受けた時に原作を読み返すことで、「父親と息子、権力とその後継者の話」である事に気付いたコッポラは、「組織的暴力団の話よりも、ある家族の年代記として撮りたい」と逆に申し出ている。つまりコッポラは、家族の絆を、この作品に抽象的な意図として刻印していると言えよう。
当時のアメリカに於いて、家族の絆はヒッピー文化の隆盛により崩壊しており、シャロン・テート殺害事件により目を覚ました大衆は、その回復を望んでいた。家族の絆は、コッポラから投影された抽象的な意図であるが、そこに更に、大衆から投影された抽象的な意図が重なることで、歴史的な大ヒットへと繋がっていく。
マフィアは、暴力装置としてのアメリカに繋がる。麻薬取引を拒否するコルレオーネファミリーは、正義ある暴力装置としての、第一次大戦、第二次大戦時のアメリカへと繋がる。しかし、正義ある暴力装置としてのアメリカは、ヴェトナム戦争の敗戦により、正義の二文字を失った。麻薬は、ヒッピー文化へと繋がる。それを拒絶したヴィトーは、古き良きアメリカを守ろうとする存在に繋がる。小さな組織の陰謀渦巻く下らない抗争は、アメリカの伝統を踏みにじったヒッピー文化へと繋がる。ヒッピー文化は、セックスとドラッグによって、インド文明が中国や日本を巻き込み数千年掛けて築き上げてきたものを容易に手に入れられると勘違いした、下らない熱狂に過ぎなかった。そして、下らない抗争を終らせる、孤独な真の指導者の到来を期待させて幕を閉じる。
そこにニクソンが登場する。彼は、世界全体を視野に入れ、大改革を断行した。
経済
新経済政策へ
1972/8/15 ニクソン 新経済政策を発表
→ 西側陣営内に於ける負担の分担
→ ドルの金兌換停止:強いドルの放棄
→ 変動相場制へ
1973 第四次中東戦争
→ アメリカ イスラエルを支援
→ サウジアラビア アメリカへの石油輸出全面禁止
→ オイルショック
→ 困惑(雰囲気)
→ アメリカ サウジアラビアとの関係改善を望む
1976 ワシントン・リヤド密約(未確認情報)
後日更新

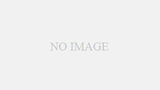
コメント